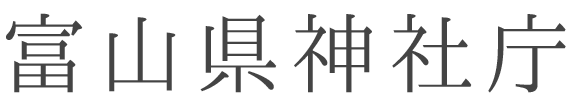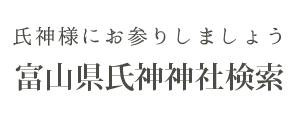楽器紹介
◆打楽器《うちもの》
鞨鼓(かっこ)
筒状の両面に皮を当てた、小型の太鼓です。台に載せ木製のばちで両面を打ちます。演奏のテンポを決定する楽器として、合奏ではリーダーの役割を果します。
鉦鼓(しょうこ)
金属製のお皿の形をした凹面を、二本のばちで少しずらすように打ちます。通常太鼓に付随して打たれる事が多く、太鼓のテンポよりやや遅れて打たれます。
釣太鼓(つりだいこ)
釣太鼓は室内の管弦に用います。片面だけを木製の太いばちで打ち演奏します。太鼓の模様は、宮廷音楽である雅楽にふさわしく美しい図柄が描かれています。
◆管楽器《ふきもの》
横笛(おうてき)
龍笛(りゅうてき)とも呼ばれる竹製の横笛です。旋律楽器で、「音取」などを除く一般的な唐楽曲では、すべてこの龍笛の音頭(主奏者)の独奏で始まります。他に高麗笛(こまぶえ)・神楽笛(かぐらぶえ)などがあります。
篳篥(ひちりき)
表面に七つの穴、裏面に二つの穴のある管に、蘆(あし)で作った舌(ダブルリード)を挿し込んで吹くたて笛です。演奏前には舌をお茶につけ、乾燥によって閉じたリードを暖め、水分によって開かせ使用します。雅楽の主要旋律楽器として用いられます。
笙(しょう)
十七本の竹管が輪の形に並べられた姿が特徴的です。演奏時には火鉢を脇に置き、あぶる事により楽器の内部を乾燥させ、鳴りを良くして演奏します。主に和音を奏で、演奏に厚みをもたせます。
◆弦楽器《弾きもの》
楽琵琶(がくびわ)
雅楽専用に使われる琵琶のことを指して「楽琵琶」と言います。他の平家琵琶、薩摩琵琶、筑前琵琶と音色も大きさも違います。日本の琵琶の仲間では一番大きく、重さもどっしりと重く、重厚な音色を持ちます。水平に構えておしゃもじのような撥(ばち)で弾きます。果物の枇杷(びわ)は琵琶に似ているからその名が付いたとされています。合奏においては一拍目の頭を決める役割を持っています。
楽箏(がくそう)
楽箏とは生田流・山田流や筑紫箏と区別するための呼び方で、雅楽専用に用いる箏を指して呼びます。十三弦で弦は黄色の絹糸で低音弦は太く、高音にしたがい細い弦を使用します。爪は細く削った竹を皮で巻き、銀色に着色した固有の物を使います。一般的な箏のように主旋律を奏でる奏法に対し、主に拍を定める打楽器としての役割が大きい楽器です。
和琴(わごん)
日本固有の神楽などに用いられる絃楽器。御琴(みこと)、倭琴(やまとごと)とも言います。一般的な十三弦の琴とは違い、六弦の素朴な音がする日本独自の楽器です。
箏と違い、手に爪は付けずに鼈甲で作った「琴軋(ことさぎ)」というピックの様な物を使って鳴らします。柱は二股の楓の小枝を皮の付いたまま使用します。
◆その他
笏拍子(しゃくびょうし)
神職、貴族の持つ笏を真二つに割った形の拍子を取る打楽器。左手に持つ笏は切り口を上にして持ち、右手の笏は切り口を左にして打ち合わせる。日本固有の神楽歌や催馬楽(さいばら:平安時代に生まれた歌物)の拍子取りに使う。
唱歌(しょうが)
笙、龍笛、篳篥の管楽器の演奏を習得するに当たり、最初に習うのが「唱歌」です。唱歌は楽器の旋律を歌にした物で、手で拍を取りながら曲の流れや構成を把握していきます。さらには暗唱できるように習得することにより楽譜を見ずに演奏する手段として雅楽を志す人にとっては必要不可欠な稽古でもあります。笙、龍笛、篳篥それぞれの楽器に合わせて歌は違います。太鼓、琵琶、箏はそれ独自の唱歌はなく、管絃の唱歌を歌いながらそれぞれの楽器を鳴らしますので、管楽器は必ずどれかは習得しないと打ち物、弾き物は演奏できません。